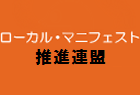公開日 2025年10月24日
2025年10月23日(木)「地方議員ができる生活困窮者対策セミナー」を豊洲文化センター(東京都江東区)&オンラインで開催しました。全国から約40名の参加申し込みがあり、関心の高さがうかがえました。
高齢化の進行や不安定雇用の増加により、生活保護をめぐる課題は複雑化しています。不正受給や貧困ビジネス、申請窓口での対応、ケースワーカーの不足など、現場の課題は多岐にわたります。こうした中で、地方議員にも多くの相談が寄せられている現状を踏まえ、本セミナーを開催しました。

会場&オンラインにて開催。生活保護制度などに関心の高い参加者が集まった
はじめに、明治大学専門職大学院ガバナンス研究科の大山典宏教授が「生活保護制度の概要と実務~利用者の法的権利を中心に~」と題して講演を行いました。
大山教授は、生活保護制度のメリット・デメリットをわかりやすく説明し、クイズ形式で参加者に考えを促しながら、制度の理想と現実、社会保険との違い、生活保護法の基本原理などを丁寧に解説しました。最後に、小山進次郎氏の著書『生活保護法の解釈と運用』を紹介し「『自立の助長』という理念・魂をぜひ皆さんに引き継いでほしい」と呼びかけました。

大山教授は、志木市役所や埼玉県庁職員などの経験をもち実務にも精通している
続いて、足立区議会議員の小椋修平氏が「地方議員は生活保護にどう向き合うべきか~対応事例と議会での取組み~」をテーマに報告しました。コロナ禍で寄せられた多くの相談事例や、メディアでも注目された実践例を紹介しながら、困窮者支援の現場で直面する課題と、SNS等を通じた情報発信の重要性を強調しました。
また、「役所に相談に行くこと自体が大きなハードル。解決に至らなくても、まず話を聴き同行すると見えてくるものがある」「個人からの相談でも同じ悩みを抱える人は必ずいる。議員として制度の改善や新たな制度の創設につなげている」と述べました。さらに、足立区での取組みとして、扶養照会や生活保護のしおり、相談カードの改善事例を紹介。全国157自治体の資料を調査し、改善を働きかけた経緯も共有しました。

コロナ災害対策自治体議員の会共同代表もつとめる小椋議員
質疑応答では、「アルバイト収入の認定方法」「シングルマザーへの支援」「地域差(級地)の見直し」「韓国との制度比較」などの質問が寄せられました。大山教授は日本の制度の悩ましい現状を伝えながらも「万能な答えはない。丁寧に話を聴くことが何よりも大切」と述べ、小椋議員も「現場に足を運ぶことでしか見えない課題がある」と話しました。
最後に大山教授から、岐阜市の改善事例が紹介されました。岐阜新聞が特集を組んだ取材をきっかけに、議会で実務運用についての質問が広がり、生活保護の運用に劇的な変化をもたらしたことです。「議会がビジョンを示せば、行政は必ず変わる。地方議員の皆さんに力を借りたい」と強いメッセージが送られました。
今回のセミナーは、制度の学術的理解にとどまらず、議員として現場でどう向き合うべきかを具体的に学ぶ貴重な機会となりました。今後も、地方議員の政策力と実践力を高めるためのセミナーを継続的に開催していきます。
(事務局・N)

最後にオンライン参加者と記念撮影
 会場では貴重な情報交換・交流も行われた
会場では貴重な情報交換・交流も行われた