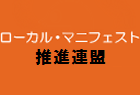公開日 2025年11月10日
2025年11月8日(土)「全国地方議会サミット2025」の2日目を法政大学(東京都千代田区)とオンライン併用で開催しました。今年は全国から330名を超えるお申込みがありました。【DAY2】では、新たな技術が民主主義へ与える影響や議会改革の傾向をふまえたうえで、これから地方議会としてどのように子ども・若者の声や政策づくりに向き合い、政策サイクルを実践していくのかを議論しました。
はじめに、【地方議会の政策づくり実践編①】として「子ども・若者との政策づくり」のセッションが行われました。まず、林紀行 日本大学法学部教授が課題提起を行いました。林教授は日本における選挙権拡大の歴史を振り返りながら「主権者教育と議会改革をセットにして制度を実装する」ことを提案しました。そして、3つの先進的な事例報告が行われました。勝山祥 富士見市議会議長による「富士高生の主張 in 富士見市議会」、笹田卓 浜田市議会副議長(前議長)による「主権者教育につながるこどもの意見の施策反映」、NPO法人DAKKO理事の田口裕斗氏による「議員との対話で 民主主義の担い手を育てる」です。
質疑応答では「学校教育の現場では政治活動と主権者教育のマッチングが難しい。どうやって熱意ある教師の方を発掘するのか」「面積がとても広く学校も多い。そのため、主権者教育を行う学校の抽出手法や考え方を知りたい」「子どもたちの政策を実現するうえで苦労したことは何か」「主権者教育の中間支援組織は他の自治体へも水平展開することが可能か」などの質問があがりました。最後に、林教授からは「ローカル・マニフェスト推進連盟が創設された初期には『地方議員はマニフェストが書けるのか』という問いをたて実践してきた。これからは、新しく『地方議員は主権者教育ができるのか』という問いにチーム議会で挑戦してほしい」と呼びかけました。





つづいて、【地方議会の政策づくり実践編②】として「議会による政策づくり」のセッションが行われました。まず、江藤俊昭 大正大学教授が問題提起を行いました。江藤教授は「善政競争=横展開に役立てるための実践事例や、継続のための手法を学ぶ」場であることを念押しし、二元代表制である地方自治の理念を強調しました。そして、3つの先進議会による事例報告が行われました。勝浦伸行 一関市議会議長による「『政策提言等の実施に関する指針』の策定と実践」、高橋英昭 横須賀市議会政策検討会議委員長による「政策形成サイクルの実践と実例紹介」、外山利章 知名町議会議長による「各常任委員会による町民起点の政策提言」です。
質疑応答では「実現した農業政策について誰が主導しどのような方法で予算はどのようにつけたのか」「議員提案条例は検証しているが、理事者側が提出する条例と扱いとどう違うのか」「4年ある議員任期の中で1年、2年の委員会任期と政策サイクルはどう効果の違いがあるか」などの質問があがりました。そして途中には、江藤教授が会津若松市議会の『議会参加ガイドブック』を投影し政策サイクルのあり方について解説する場面も。さらに飛び入りで、財政にしっかり関わる政策サイクルを紹介する目的で、会場にいたローカル・マニフェスト推進連盟共同代表の川上文浩 可児市議会議長が「予算決算審査サイクル」について発表を行いました。
最後に江藤教授は「今、20年前には考えられなかった議会改革が進められている。どれが正しいという答えはないが、自分たちにあった取組みをTTP(徹底的にぱくる)してほしい。住民自治の根幹は議会だということを念頭に、後世の人たちに影響を与えるような政策サイクルをつくり、新しい時代をつくっていってほしい」とまとめました。





各議会での実践に向けて、多くの事例とヒントを得た2日目の午前中。この後、昼食休憩をはさんで、北川正恭 早稲田大学名誉教授【LM最終講義】セッションへと続きます。
(事務局・N)
【DAY1】炎上の時代とSNS・AI、議会改革度調査 開催レポート
【DAY2】北川正恭教授【LM最終講義】開催レポート